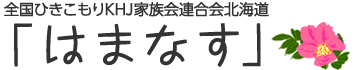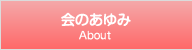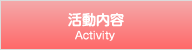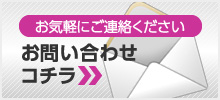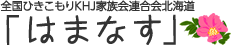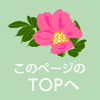ごあいさつ

ひきこもりの数は年々増えており、内閣府調査(2022年調べ)によりますと、全国で約146万人のひきこもりがいると推計されています。
それなのに、家族会に参加する人は、それほど多くなっていません。
まず考えられることとしては、親が高齢化していることです。一時「80-50問題」が話題に上っていましたが、今では「90-60問題」へと変わりつつあります。親が高齢化し、会場へ足を運ぶことが困難になりつつあるのです。
もう一つの理由として考えられるのは、親が会場へ足を運んで熱心に話を聴いても、そう簡単にひきこもりが解決するものではないということです。特に父親は数度通った後あきらめて来なくなってしまう傾向が見られます。これまで汗水たらして働き、家族を養ってきた父親としては、世の中の変化を直視し、これまでの価値観を変えることは極めてむずかしいことと言えます。
家族会では、率直に家の様子や子供の様子を話し合います。そこには、対等な関係があります。反論や意見を言ったりせず、ひたすら話し、聞きます。そうすることによって、「悩んでいるのは自分だけではない」という安心感が得られます。また、他では言えないことでも何度も繰り返し自分の言葉で話すうちに、ひきこもりに関する理解が深まってくるのです。
特に、父親の言葉の中に多く見られるのですが「いつになったら働くつもりなんだ?」「親が死んだら、どうやって生きていくつもりなんだ?」「将来のことをどう考えているんだ?」これは、父親が退職して家に居るようになってから家族関係が悪化したという事例が多くあることからもわかります。ひきこもる子どもに対して言ってはならない言葉<禁句>なのです。この禁句を理解するまでに、父親は相当の時間を必要とするのです。親が子供を説教すれば、子どものひきこもりが治るわけではありません。
大事なことは、家族間の好ましいコミュニケーションを取り戻すことです。どんなに立派な言葉をかけても、相手に通じないだけでなく、傷つけてしまっては何にもなりません。今ある家族の中で、相手を尊重し、好ましいコミュニケーションを図ることが親の仕事と言えます。
「待つ」というのは、放っておくということではなく、適切なコミュニケーションを積み重ねながら、本人がエネルギーを蓄えるのを待つということです。
家の中で親が機嫌よくしていることがひきこもる子どもの薬になります。そして親が反論せず、ただ聴いてくれることが本人にとって薬になります。
表面上、ひきこもる子供に変化がみられないとしても、内部では絶えず変化しているのです。「ある日、突然本人が動き出したという事例もあります。
一人で悩まずに、どうかひきこもり家族会「はまなす」へ足を運んでください。お待ちしています。
全国ひきこもりKHJ家族会連合会
北海道「はまなす」